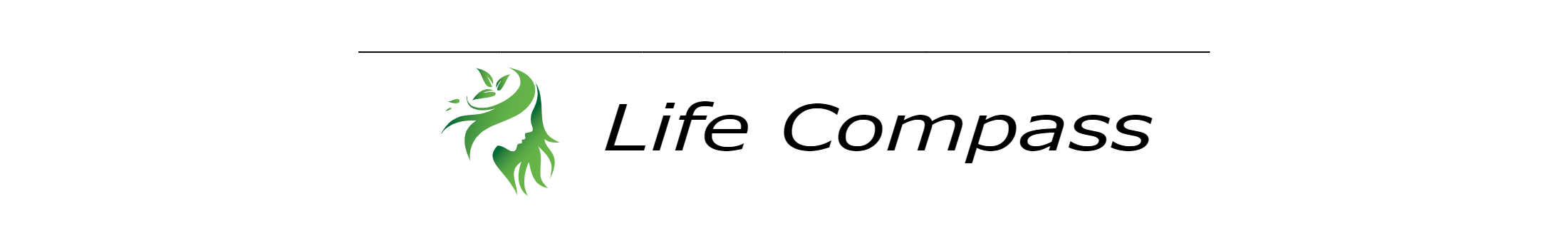話を聞いてて「この人、いったい何が言いたいんだろう?」って思うこと、ありませんか?

一生懸命に話してるんだけど、一般論ばかりで自分の意見を一向に言わない。
説明ばかりで結論がなかなか出てこない。
話が長すぎて、何の話をしていたのか途中で分からなくなる。
反対に、話の分かりやすい人もいますよね。
日常会話でも、会社の会議やプレゼンでも、不思議と話の内容が頭の中にスっと入って来る。
頭を働かせなくても相手の言いたいことが自然と分かってしまう。

そういった、短い言葉でも上手に自分の考えを相手に伝えることの出来る人がいます。
この両者って、どこが違うのか分かります?
ポイントは「結論をどこに持ってくるか?」です。
話の分かりにくい人は、ひたすら説明ばかりが続いて最後に結論を持ってくる。
イメージとしては
説明→説明→説明……→結論
こんな感じです。
もしくは一般論ばかり話して結論そのものが無かったりする。
反対に話の分かりやすい人は、最初に結論を言い、その後にその結論に至った経緯を説明して、最後にもう一度結論を述べて締める。
「私はこう考えます。なぜそう考えるのかというと、こういう理由があるからです。よって、こういう結論に至りました。」
つまり
結論→その理由や説明→結論
こんな感じです。
ちょっと例を挙げてみましょう。
例えば「新しいプロジェクトの進行状況についての報告」をするとします。
そこで話の分かりにくい人だと
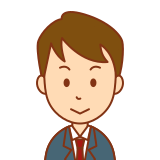
さて、今回のプロジェクトの進捗についてお話しします。
まず最初に問題になったのは、スケジュールの調整でした。
あの会議での意見の食い違いが原因で、全体のタイムラインに影響が出てしまいました。
それから担当者がいくつかのタスクを重複して行ってしまったため、リソースの無駄が生じてしまいました。
その後チームのメンバーと何度もミーティングを重ねて、問題の根本原因を突き止めました。
それで最終的にこの問題を解決するために、タスクを見える化し、作業の可視化と共有を図るという新しいアプローチを試すことに決めました。
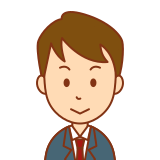
今回のプロジェクトの進捗ですが、タスクを見える化し、作業の可視化と共有を図るという新しいアプローチを試みることにより現在の課題は解決しました。
具体的にはスケジュール調整とリソースの無駄が問題でしたが、それに対処するために全体の作業内容の把握と担当者の再配置などを行った結果、プロジェクトは予定通り進行できる見込みです。
この違い、分かりますでしょうか?
最初の人のように結論ではなく説明から入ってしまうと、聞き手は「この人は一体何を言おうとしているのか?」「どんな結論を出そうとしているのか?」をずっと想像しながら聞くようになりますよね。
つまり聞き手が頭を働かせながら聞き続けないといけないわけです。
これだと聞き手は疲れるし、話もボンヤリして理解しにくくなります。
これが二番目の人のように最初に結論を言うと、話の全体像や方向性もすぐに分かるし、聞いている人が内容も追いやすくなるため、話が断然理解しやすくなります。
また結論の後に続く説明も、結論に沿って話していくので聞き手も迷うことなくスムーズに理解できる。
つまり「分かりやすい話」と「分かりにくい話」の違いは、結論を最初に伝えるか、後に伝えるかに大きく依存するということ。
結論を最初に持ってくる話し方は、聞き手にとって「話の要点が何か」を早い段階で理解できるため、情報が整理されてスムーズに受け入れられる。
一方で結論を後に持ってくる話し方や結論が出ない話は、聞き手が話の流れを追うのが難しく、混乱や誤解を招く原因となる。
よって結論を最初に、そしてその後にその結論に至った理由を説明するスタイルに変えるだけで話がグっと分かりやすくなるのです。
またついでに言うと、結論から話す人というのは「賢い人」として見られやすくなるという利点もあります。
結論から話し始めることによって、「この人の話は分かりやすいな」「この人は話の要点を押さえてるな」といった印象を相手が持つようになるからです。
知的で賢い人に見られたい人にはオススメです(笑)
ということで「結論から話す」という習慣を、ぜひ身につけてみてください。
これにより会話がよりスムーズになり、相手との信頼関係もよりしっかりと築かれていきますので。
仁より